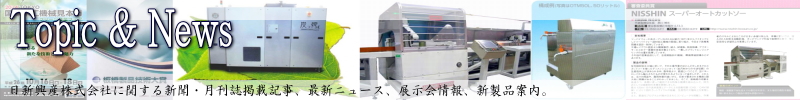 |
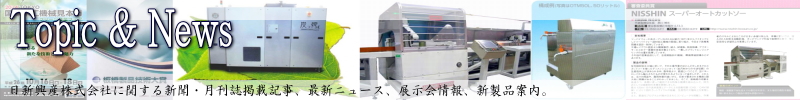 |
| 全国規模の生販両団体が協調して 「木工機械メーカーの全国団体(全国木工機械工業界、以下=全木機)と同商社の全国組織(全日本木工機械商業組合、同=全木機商組)が強調し、製販両業者が一体となった新たな展示会が今後は必要」。そうなれば「その開催に合わせて作る方はどんどん新製品を発表し、売る方もそれをどんどん売っていく」ことができるからだ。ただ、そのためには「現在ある東京、名古屋、大阪の三展を一つに調整しなければ、現状ユーザーの設備動向に呼応したアプローチができない」と、現状下での木工機械展のあり方について言い切るのは四月某日、別件で訪ねた二×四住宅の設備メーカー、日新興産(東京都板橋区常盤台)の原口博光社長。 昨年十一月にも本紙に登場し、過激な内容で展示会問題を切り出したが、理論派で知られる原口氏の矛先は今回「その開催地は東京でなければいけない」とまでに及んだ。はたしてその理由は―――。 |
 |
| 原口 博光氏 日新興産(東京)社長 |
|
業界の規模が三分の一以下までに縮小しているのに、まだ二年間に三展がバラバラに開かれているようでは、業界が一つにまとまった発信やアプローチがユーザー業界にできるわけがない。それなのに開催規模縮小による自然淘汰を三展に待っているようでは、その時点で業界のパワーも同時に落ち込んでしまう。 「各展の淘汰待ってたら業界全体のパワーが落ち込んでしまう」 だから展示会の開催をビジネスとしてきた三展の歴史的役割は、もう現状ではそぐわないことを物語っているわけで、今後は三展主催者の開催撤退も止むを得ないものとして、実勢にあった新たな組織による展示会が強く求められる。それは全国団体の全木機と全木機商組が主導するものに他ならない。 業界の母体である両団体は会員数の減少に直面し、その維持さえ危ぶまれている。企業活動には私的な面と公的な動きがあるが、業界がここまで縮小しているのにまだ利己的に終始していいわけがない。仮にもそれができるのは業界が存在しているからだ。だから、そんな現状の打開策としても開催を是非、両団体で事業化すべきなのである。 「現状下に組合職員の給与を組合員の会費だけで賄う例は他の工業界に見当たらない。多くは展示会を事業化している」と経済産業省の担当官も指摘しているように、それは絶対に欠かせないのである。 「多くの工業会は展示会開催を事業化している」経産省担当官 そして、その開催地はなんといっても東京(東京ビッグサイト)がベストである。業界の実態はもはや心情的レベルにないほど厳しいものの、歴史的には名古屋を意向するメーカーが業界には少なくない。しかしバックグラウンドの関東地方には世界でも最大市場の約四千万人の消費者が控えているし、その波及効果や木工周辺の関連需要、また経済的、文化的役割なども東京は他地域より群を抜いて大きい。 しかも、先に全木機などの陳情活動によって実現した優遇税制(生前贈与の非課税枠が三千五百万円に拡大など)の導入などに象徴されるように、これからは政治との係わりや支援も強く望まれることを考えると、やはり本省庁のある東京しかない。 ただ、東京開催に問題がないわけではない。これまで一年に一つの展示会を支援してきた全目機は先の理事会(四月一六日)で、二〇〇四年から「二年に一展」に改めた。その場合、その支援展の名を公表するかは今のところ未定だが、仮に順送りになれば、そんな長い開催間隔で会場(ビッグサイト)が予約確保できるかが不安視されるからだ。そうなると、現在の東京展自体も支援から外れた年の開催は規模がより縮小することが必至だが、その前に会場の確保さえ難しくなる。だから既存展主催者は展示会事業を一度白紙に戻すなどして、一つにまとまって業界をそれぞれ支えていく必要がある、という図式が簡単に成り立つわけだ。 |
|
| 掲載メディア 樹事報 2003 /5/20 (火曜日) 発行所 木へン舎 |
|
 |